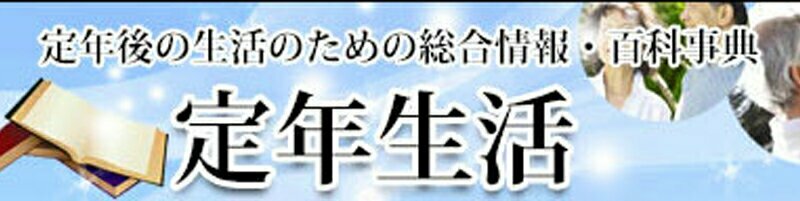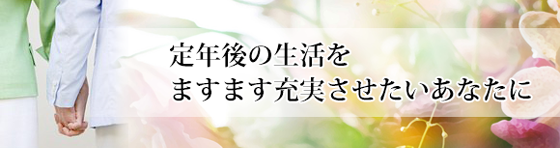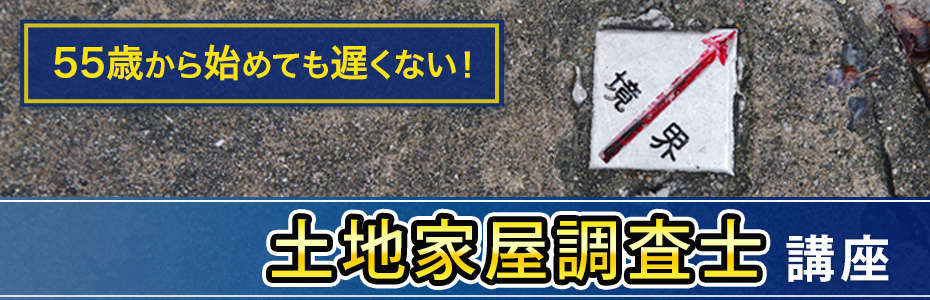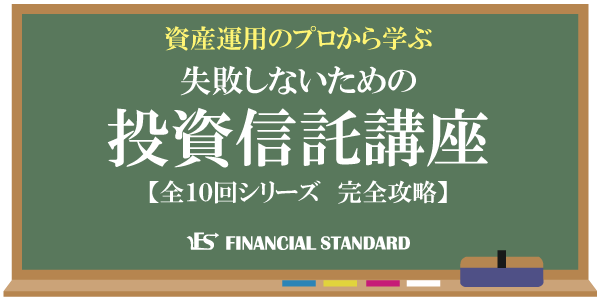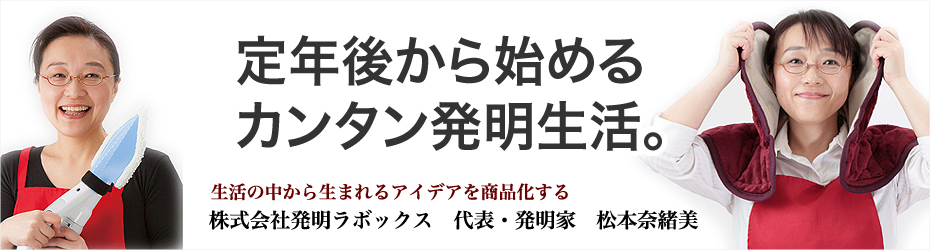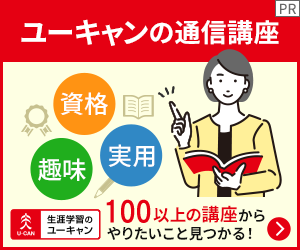司法書士と土地家屋調査士 その業務の相違点
2025/3/27不動産登記に関わる専門家には司法書士と土地家屋調査士がいる
私たちが府御動産を購入する際に必要なってくる手続きの一つが権利者を明確にする世間に伝えるための不動産の公示という登記手続があります。
【不動産登記法1条】
この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。なんだか難解そうですが、かみ砕いて説明しますと、不動産に関する登記には「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2つがあります。これらを「公示」することで国民の権利の保全が図られるということになります。私たちが不動産を購入する際に、登記移転を自分でやらなければ、登記申請のための書類を整えるの専門家がいます。
この専門家こそ、司法書士や土地家屋調査士と呼ばれる専門家です。この2種類の専門家は何が異なるのでしょうか?今回は同じ不動産登記申請の専門家である司法書士と土地家屋調査士の違いについてご説明したいと思います。
不動産登記法における不動産とは?
まず大前提として不動産登記法における「不動産」とは何でしょうか?
不動産登記法では第2条で「土地又は建物をいう」とされています。
ここで注意すべき点をお伝えしましょう。「土地」のうち、河川の敷地や海底は所有権の多少にならない、即ち不動産登記法における「不動産」としては扱われないということになっています。
次に建物はどうでしょうか?建物は新築によって不動産登記の対象になります。そして解体、朽廃、消失によって不動産登記の対象からなくなることになります。ではどの程度、建築が進むと建物と呼べるのでしょうか?
ここで建物に認定される基準とは不動産登記規則で定められています。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であってその目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない」(規則111条)とされています。そして完成した建物についてそれが「建物」にあたるかどうかについての建物認定基準については不動産登記法準則77条1号、2号で以下の様に定められています。
不動産登記の対象には表示と権利の登記の2種類がある
不動産登記法によれば、不動産登記には「表示」と「権利」の2種類があることが分かります。
このうち、不動産の表示とは、不動産の物理的状態を切らかにし、他の不動産と区別できる程度に当該不動産を特定することで不動産に関する権利の対象、範囲を明確化することにあります。
「不動産の表示」に関する登記を「表示に関する登記」(不動産登記法第2条第3号)と呼び、これが記録される部分を「表題部」と呼んでいます(不動産登記法2法7号、12条)。このようにして、「表示に関する登記」の部分を通じて個々の不動産が特定されるならば、その不動産ごとにそこに生じた種々権利変動を登記することが可能になります。
権利の変動についても不動産登記法に規定があります。不動産登記法では3条1号から9号に掲げる権利の「保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅」という言葉が用いられ、これらの権利の保存等に関する登記を「権利に関する登記」といいます(不動産登記法2条4号)。権利に関する登記が記録される部分を「権利部」と言います(不動産登記法2条8号、12条)。
登記場に申請する職業専門家も2種類いる
私たちが不動産を購入した際に自分で登記申請をする方は珍しく、多くの方は専門家に依頼すると思います。
そこで登場するのが司法書士と土地家屋調査士と呼ばれる職業の方々です。前述した「表示に関する登記」を土地家屋調査士が行い、「権利に関する登記」は司法書士が行います。
ちなみに土地家屋調査士における表示に関する登記の代理申請は申請全体の95%以上、司法書士による権利に関する登記の代理申請は全体の90%以上を占めています。弁護士による代理人訴訟は77%ほどだそうですので、以下に代理人申請が多いかが分かります。次に司法書士と土地家屋調査士の歴史についてみてみましょう。
PR表記
土地家屋調査士と司法書士の業務の違い
土地家屋調査士と司法書士は共に不動産登記を使う職業専門家です。この2種利の専門家の歴史的経緯についてみてみます。
土地家屋調査士の歴史
土地家屋調査士は国家資格の一つです。不動産の表示に関する登記(表題登記)について必要な土地・家屋に関する調査や測量、表題登記の代理申請、また、土地の境界の位置を特定する筆界特定などが主たる業務です。そこで建物の表題登記の依頼先は、土地家屋調査士になります。
土地家屋調査士の歴史は不動産登記ではなく、租税聴衆のための帳簿である土地台帳・家屋台帳に携わっていた人です。
土地台帳は、明治6年に導入された地券の制度に由来します。
家屋については、明治32年以降、府県税、地方税として家屋税が付されるようになります。
戦後、地租税、家屋税は地方に移管され、府県税となります。昭和25年には地租税、家屋税も廃止され、市町村が固定資産税を徴収することになり、それまであった土地台帳、家屋台帳は不要になりました。
これまでこの台帳の登録業務に携わっていた方々を「土地家屋調査士法」の制定により、法務省所管の国家資格である土地家屋調査士と称することになりました。当初の土地家屋調査士の業務は土地家屋に関する測量、登記がメインでしたが、平成16年に不動産登記法が改正され、筆界特定の制度が導入され、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民事紛争解決手続が業務内容に加えられました。
そこで建物の表題登記の依頼先は、土地家屋調査士になります。
建物の表題登記については、不動産登記法第47条に次のように定められています。「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない」
司法書士の歴史
司法書士は弁護士や公証人と並ぶ日本最古の職業法律家です。
その起源は明治5年に遡ります。司法職務定制において現在の公証人、司法書士、弁護士の起源と言われています。
大正時代に入ると、「司法代書人法」により、国家資格になります。司法代書人としているのは、行政代書人(現在の行政書士)と区別するためです。
昭和25年に司法書士は、「他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする」と規定しています。昭和42年には申請代理に権限も法律に明記されます。私たちが家の新築、新築の家の購入後に法律通り表題登記を行ったとしても、「この家は私のもの」と家の所有権が明確になるわけではありません。
所有権を明確にするためには「所有権保存登記」を行う必要があるからです。この申請代理を行うのが司法書士というわけです。所有権保存登記は、表題登記と違って法律で義務付けられてはいませんが、所有権保存登記を行わないと、その家が自分の家であることを公的に証明できず、第三者に対して不動産の所有権を主張できません。そのため所有権保存登記はきちんと行うべきものです。平成14年には簡易訴訟代理等関係業務の獲得により司法書士の社会的地位は飛躍的に上昇します。
この改革により140万円以下の少額訴訟について司法書士が訴訟代理人となることが出来るようになりました。依頼先による違いの比較まとめ
これまでの説明を表にまとめると以下のようになります。
この様に見てみると土地家屋調査士と司法書士は同じ登記実務の業務であってもかなり異なる業務であることがお分かりいただけると思います。
また土地家屋調査士の平均年齢は「56歳」とされ、50代以上の方が中心の士業でもあります。
定年生活ではそんな土地家屋調査士にまつわるコラムを定期的に配信しております。同じ不動産登記に関わる業務で司法書士は聞いたことがあるけれど、土地家屋調査士って何?という方にはぜひ、ご覧頂きたいと思います。
(文責:定年生活事務局)
定年生活ではLINEのお友達を募集しています☆以下のQRコードからお友達登録をしていただきますと、LINEだけでのお役立ち情報をお届けします。

定年生活.com トップ» 暮らす » 司法書士と土地家屋調査士 その業務の相違点